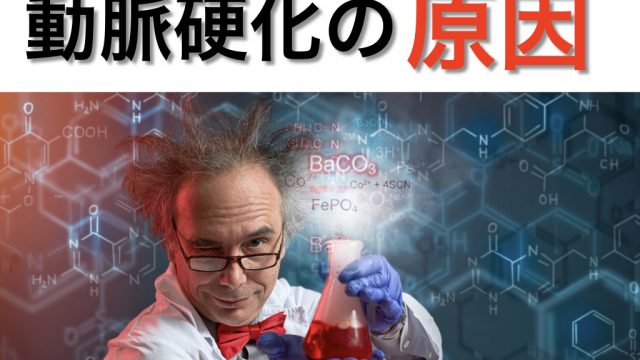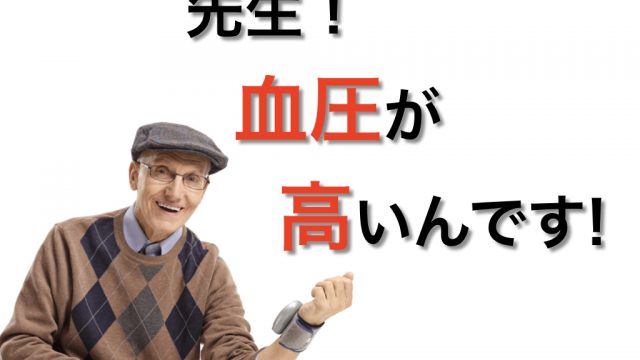今回は動脈硬化「超まとめ」薬剤編。
薬以外はコチラ。

中性脂肪はコチラ。

コレステロールはコチラ。
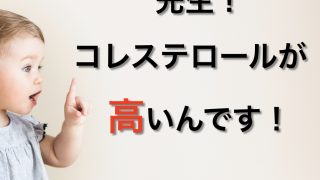
検査はコチラ。

動脈硬化の原因についてはコチラ。
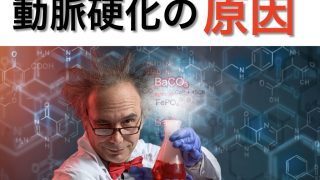
血圧との関連
日本人の高血圧の85〜90%は原因のはっきりしない「本態性高血圧」といわれています。
日本人の高血圧の85〜90%は原因のはっきりしない「本態性高血圧」。
その「本態性高血圧」の実態とも言えるのが「動脈硬化」です。
「本態性高血圧」の原因は「動脈硬化」。
このため「動脈硬化を改善」できれば「高血圧」が改善できます。
実際に動脈硬化の改善と共に血圧が降下し、薬がいらなくなった症例には事欠きません。
本態性高血圧の「治療」は「動脈硬化を改善させる事」です。
本態性高血圧の「治療」は「動脈硬化を改善させる事」。
延々と降圧剤を投与し続ける事「だけ」では「対症療法」で、病気を「治して」いません。
血圧が上がる原因を放置して、抑えつけているだけです。
血圧が上がる原因を放置していれば、どんどん血圧が上がり、どんどん薬が増えます。
原因を放置して延々と降圧剤を投与し続ける「だけ」なのは、病気を治していない。抑えつけているだけ。
薬が要らなくても健康を保てるようにするのが「治療」です。
薬が要らなくても健康を保てるようにするのが「治療」。
薬が必要なうちはまだ健康ではありません。
コレステロールとの関係
中性脂肪についてはコチラを。

コレステロールが高い場合に、よくされているのが「コレステロールが高いので薬を飲みましょう」という説明です。
コレステロールが高いと「コレステロールが高いので薬を飲みましょう」と言われる。
これは省略されている行間を埋めると、
「コレステロールが高いと動脈硬化になります。
動脈硬化すると血管が詰まって脳梗塞や心筋梗塞になる可能性があります。
これは危険ですので、コレステロールを下げる薬を飲みましょう。」
という事になります。
つまり、「高コレステロール=動脈硬化」なので危険です、という説明です。
しかし、この2つはイコールではありません。
「高コレステロール=動脈硬化」ではない。
そう、コレステロールが高くても動脈硬化をほとんどしていない人が多くいます。
コレステロールが高くても動脈硬化をほとんどしていない人が多くいる。
この場合にはコレステロールを下げる薬は全く必要ありません。
なぜなら、動脈硬化していないからです。
閉経前の女性がこのパターンの事が多いです。
女性ホルモンが動脈硬化を防いてくれています。
もちろん、実際に動脈硬化がかなり強く血管が詰まったり、詰まりかけている場合には抗血栓薬(一般に「血液サラサラの薬」)とコレステロール降下薬を飲まないとさらに血管が詰まる事があります。
これを見分けるためにするべきは何でしょうか?
「コレステロールが高い」→「即薬」ではなく、
「コレステロールが高い」→「動脈硬化の検査」ですね。
検査をして、動脈硬化があるなら、その時はじめて薬を検討するべきです。
「コレステロールが高い」→「即薬」ではなく、
「コレステロールが高い」→「動脈硬化の検査」が本来の流れ。
検査についてはコチラ。

繰り返し血管が詰まる人が実際にいます。この場合には薬は必要です。たとえ、糖質をオフしていても、です。
繰り返す血管が詰まる人が抗血栓薬などをやめてしまうとそのまま血管がさらに詰まり
命に関わる事があります。糖質を控えていても、詰まります。
繰り返し血管が詰まる人は、再発予防のために薬が必須。やめてはいけない。
コレステロールが高いけど、動脈硬化してない時は?
コレステロールが高いだけで、全く動脈硬化をしていない。
頸動脈エコー検査で、プラークもない。
ABI検査でも血管の詰まりもなく、baPWVの数値も低く血管も固くない。
CTでも血管に石灰化像がない。
などなど、各種検査でも動脈硬化の兆候がない、という場合。
当然ながら、薬は不要です。
なぜなら、動脈硬化していないから。
診断書などが必要な場合には動脈硬化の検査をしてもらい、「動脈硬化していないので薬は不要」というような診断書を書いてもらうと良いでしょう。
ただし、動脈硬化をせずに「コレステロールが高い=絶対に薬が必要」という医師も多くいます。その場合は主治医を変更してください。
既に以前に血管が詰まった事がある
もの凄い動脈硬化をしている。
既に詰まった血管がある。
脳梗塞や心筋梗塞を起こした事がある。
このような例は重症例です。
このような例では
抗血栓薬(いわゆる血液サラサラの薬)
や
コレステロール低下薬、中性脂肪低下薬
などが必要となります。
コレステロールが高いと出される薬「スタチン」
コレステロール低下薬については一般的に処方されるのは「スタチン系薬剤」です。
この薬については2014年8月25日に日本脂質栄養学会が日本動脈硬化学会の理事長に宛てた「コレステロール低下医療に関する緊急提言」を出しています。
なお、「日本動脈硬化学会」の方は下記の製薬会社からの賛助を受けています。
http://www.j-athero.org/outline/sanjo.html
賛助会員一覧
あすか製薬株式会社
アステラス製薬株式会社
アストラゼネカ株式会社
MSD株式会社
大塚製薬株式会社
小野薬品工業株式会社
科研製薬株式会社
キッセイ薬品工業株式会社
興和創薬株式会社
シミックホールディングス株式会社
積水メディカル株式会社
第一三共株式会社
大日本住友製薬株式会社
武田薬品工業株式会社
田辺三菱製薬株式会社
帝人ファーマ株式会社
日本ケミファ株式会社
ノバルティスファーマ株式会社
バイエル薬品株式会社
持田製薬株式会社
日本脂質栄養学会の方はコチラからの賛助を受けています。
http://jsln.umin.jp/about/sanjo.html
2019年度 賛助/協賛会員名簿 (2019年7月17日現在)
太田油脂株式会社
キユーピー株式会社
株式会社スギヤマ薬品
株式会社ノーベル
マルハニチロ株式会社
株式会社明治
株式会社大塚製薬工場
倉持産業株式会社
有限会社湘南予防医科学研究所
株式会社オーサン
特定非営利活動法人アルコイリス
一般社団法人大日本水産会
緊急提言自体は、こちらを参考にして下さい。
「コレステロール低下医療に関する緊急提言」
http://jsln.umin.jp/pdf/topics/Teigen140820-1.pdf
コレステロール低下医療に関する緊急提言
「コレステロール値は低ければ低いほど良い」という説に従い、「背景のリスク因子にもとづきLDL-C値の上限値を決め、それ未満に保つことを根本とする医療」が行われてきました。しかしこれには臨床的エビデンスがなく(長寿GL2010)、米国における最新のコレステロールガイドライン(ACC/AHAGL2013)でも、その根本理念は放棄されました。日・米の医療分野で代わりに導入されようとしている10年粥状硬化性疾患死亡(発症)確率(10年-リスクと略)は、臨床的に適用しうるという証明がなされておらず、また多くの臨床研究の結果と合いません。この新指標の導入によりスタチン適用者が倍増すると推定され、すでに欧米の多くの専門家が重大な懸念を表明しています。
一方、スタチンの作用メカニズムが生化学的に解明され、「スタチンは冠動脈心疾患を予防することなく、逆に動脈硬化を促進させ心不全を発症させる」ことが明らかとなってきました。また「スタチンは糖尿病を新規発症させ、発癌作用、催奇性を示し、中枢・末梢神経障害をひきおこす」ことが生化学的にも臨床的にも明らかにされてきました。高コレステロール値は長寿の指標であり、スタチンあるいは他薬との併用によりLDL-C/HDL-C比を下げると、上述のような多くの害がひきおこされ、総死亡の上昇につながると報告されています。
現在、世紀のスタチン薬禍が進行中であると考えられ、これを拡大しないよう生化学的研究の進歩を含めた十分なインフォームドコンセントを実施され、また適切な対策を講じられるよう、コレステロール低下医療を積極的に推進してこられた貴学会に提言させていただきます。
(強調表示は水野による)
このように、スタチンと動脈硬化、心不全、糖尿病、発癌、催奇性、総死亡率上昇などの関連について書かれています。
私も実際にLDLコレステロールが高かったため、スタチンを飲んでいました。
スタチンの内服中はずっと強い不眠があった事はこの講演でお話している通りです。
スタチンの内服をやめたらすんなり眠れるようになりました。
他のコレステロールを下げる薬は?
コレステロールに関してスタチン以外はエゼチミブ(薬剤名:ゼチーア)があります。
小腸からのコレステロールの吸収を抑える薬剤です。
以前に血管が詰まった事がある症例などしっかりコレステロールを下げる必要がある場合には、よくエゼチミブを処方していました。
他には、ナイアシン(ビタミンB3)製剤の「ペリシット」がありますが、あまりコレステロール値は下がりません。これは投与できる量が少ないためです。ナイアシンについては「薬以外編」で記載します。
他にもイオン交換薬、植物ステロール、などがあります。
さらに家族性高コレステロール血症で使われるMTP阻害薬、PCSK9阻害薬というのも最近では発売されています。
中性脂肪を下げる具体的な薬は?
この系統の薬剤は種類が少ないです。
強い作用があるのは「フィブラート系薬剤」のみです。
腎機能低下があると少量だったり、使えなかったりします。
あとは、「EPAの最大量投与(1日2700mg)」があります。
EPAの最大量投与の方がフィブラート系薬剤よりも副作用は少ないですが、その分、中性脂肪を下げる効果も少なめです。
単に数値を一時的に下げるだけなら断食した状態で採血をすれば低い中性脂肪の検査結果となります。
抗血栓薬(血液サラサラの薬)は?
最も強いタイプはこの2つ。
・ワルファリン
・DOAC
そこそこ強いタイプはこの2つ。
・クロピドグレル
・シロスタゾール
弱めのタイプはこの5つ。
・アスピリン
・EPA
・イブジラスト
・リマプロスト
・ベラプロスト
ワルファリン(最も強い)
ワルファリンは古くからある薬です。
よく「納豆が駄目」と言われる薬です。
ワルファリンはビタミンKをブロックする薬です。
納豆にはビタミンKが豊富に入っているためワルファリンの効果がなくなってしまいます。
このためワルファリンを飲んでいる場合には「納豆禁」となります。
また飲む量の調整が大変な薬で、特に飲みはじめには採血検査を頻繁にしなければなりません。
しかも安定しているように見えても、急に薬の効きが落ちたり、逆に効きすぎたりするので、飲み慣れている時にも油断ができません。
古くからあるので薬自体のお値段はお安いです。
DOAC(最も強い)
発売当初はNOACと呼ばれていました。
最近ではDOACと呼ばれます。
※略語注
新規経口抗凝固薬 (novel oral antico- agulants:NOAC)
直接経口抗凝固薬 (direct oral anticoagulants: DOAC)
4種類あり、どれも最近発売された薬剤です。
1錠あたりのお値段が高い事でも知られています。
こちらの場合は、納豆を食べても効果が変わりません。
繰り返しますが、お値段がお高い薬です。
ワルファリンと比べて効果が安定しているのが特徴です。
強い血液サラサラ効果があるので当然、出血のリスクはあります。
貧血が進行してしまう事もしばしばあり、注意が必要です。
お高いですが、ワルファリンの効きの不安定さは半端ないので、どちらかを選べるなら、DOACの方が良いでしょう。
ワルファリンのように、知らないうちに急に効きすぎたり、急に効かなさすぎたり、しているのはとても厄介です。
なお、心臓の弁膜症などがあると、DOACは適応とならず、実質的な選択肢が「ワルファリン」だけになってしまいます。
クロピドグレル(そこそこ強い)
割とクセがないタイプの薬剤です。
副作用は、出血の他に血液と肝臓などにきます。
血液では、血小板、白血球が減少したり、再生不良性貧血の報告があります。
肝障害では、急性肝不全、肝炎などのリスクが報告されています。
心臓の血管にステントを入れるとアスピリンと共に処方されますが1年くらいたって1種類の抗血栓薬にする場合にはアスピリンが残る場合が多いです。
最近では、プラスグレル塩酸塩(エフィエント)という薬剤も心臓カテーテル治療後に処方されるようになっています。
シロスタゾール(そこそこ強い)
こちらは心臓の動脈硬化の場合には使われません。(保険適応が無い)
慢性動脈閉塞症と脳梗塞の場合に使われます。
認知症の手前、軽度認知機能障害での認知機能の改善の報告は一時、話題になりました。
国循で認知症予防!?
http://www.ncvc.go.jp/about/excellence/11.html
シロスタゾールの副作用は出血の他には心臓などにきます。
脈が速くなる、心不全になる、心不全が進行する、などです。
アスピリン(弱い)
高齢者で施設に入っている場合によく内服しているのが「アスピリン」です。
1日1錠でよく、錠剤の大きさも少なく、お値段もお安い、という特徴があります。
しかし、胃潰瘍や十二指腸潰瘍のリスクが(オッズ比で)約3倍になります。
このため、胃薬をセットで処方されます。
EPA(弱い)
健康維持のためには少量のEPA(1日300mg程度)でも効果があるかもしれません。
しかし、既に動脈硬化をしていてそれを良くしよう!という場合には大量のEPAが必要になります。(最低でも1日1000mg以上)
私が治療で指標にしているのは「EPA/AA比」です。
この数値が1.0以上になると動脈硬化が改善される可能性があります。
通常の生活をしていると「EPA/AA比」は0.1〜0.3程度です。
亜麻仁油、紫蘇油、荏胡麻油を日常的に摂取している場合には0.5程度になります。
EPAを多く含むと言われる「鯖缶」を毎日1缶、1ヶ月食べてEPA/AA比を調べた事がありましたが(患者さん自身がご希望された)、残念ながら全く数値が変わりませんでした。
毎日刺し身をいっぱい食べる位でないとEPA/AA比は変わらないようです。
EPA/AA比を1.0以上にするためには、EPAを毎日 3000mg程度摂取する必要があります。
なお、EPAだけでなくDHAが含まれているものもあります。
DHAが混じっているものの場合、DHAがEPAの吸収を一部妨げるためEPA/AA比が上がりません。
EPA/AA比を1.0以上にするためには「EPA単独」のものを毎日3000mg程度摂取する必要があります。
特にサプリメントはDHAが入っているものや、EPAの量や純度が不足しているものばかりですので注意が必要です。。
EPA単独で高純度、1000mg含まれているサプリメントなども探せばあるので自分で飲む、というような場合にはそういったものが良いでしょう。
というか、今のところサプリメントでは1種類しかありません。
純度がほぼ100%に近く、1カプセルにEPAが1000mgも含まれています。
完全に医薬品グレードです。
ですが、このサプリメントを私が一度紹介してからiHerbでは常に売り切れています・・・。
Carlson Elite EPA Gems (1000mg)
https://jp.iherb.com/pr/Carlson-Labs-Elite-EPA-Gems-1000-mg-120-Soft-Gels/13839
今だに売り切れています・・・売り切れ続けて、はや数年が経ちます。
iHerbのEPAサプリメントは数年間、ほぼずっと売り切れ中。
iHerbではない「All Star Health」ではかろうじて在庫がある事があります。
https://www.allstarhealth.com/ja-us/f/carlson-epa_gems.htm
ただし、海外製のものはカプセルが「超巨大」なので、飲む場合には覚悟が必要です。
なお、私がDHAやDHA入りのサプリメントを勧める事はありません。
DHA自体の効果は全く証明されていないためです。
DHAが効果があった、というのは全てEPAが混じったものを使っています。
DHA製品はお勧めではない。
イブジラスト
先発品の薬剤名は「ケタス」です。
「気管支喘息」と「脳梗塞のめまい」に保険適用があります。
弱い血液サラサラ効果があります。
それ以外の効果が特徴的です。
添付文書です。
http://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/ResultDataSetPDF/230109_4490010N1021_1_21
【薬効薬理】
1.脳血管障害に対する作用
(1)臨床薬理作用
1)脳血流量増加作用 脳血管障害患者において、脳血流量を増加させた(PET)7)。
2)内頸動脈平均血流量改善作用 慢性脳循環不全症患者において、総頸動脈の平均血流量を増加 させ、循環抵抗を低下させた8)。
3)血小板活性化抑制作用 脳血管障害患者において、血小板の活性化を抑制した9)。
4)血小板凝集抑制作用 脳血管障害患者において、血小板凝集を抑制した9)10)。
5)血管内皮保護作用 脳梗塞患者において、血管内皮細胞接着分子の発現を抑制し
た11)。
(2)基礎薬理作用
ホスホジエステラーゼ阻害作用 RT-PCR法によりクローニングしたヒトの心および脳のホスホジ エステラーゼの活性を阻害した12)。
1)血管拡張作用 摘出イヌ脳底動脈においてプロスタサイクリンによる血管弛緩 作用を増強した13)。 また、脳梗塞モデルラットの脳局所血流量を増加させた。その 増加率は正常ラットと比較してより高かった14)。
2)抗炎症作用 マウスのグリア細胞からのTNFα及びNOの産生を抑制した15)。 また、慢性脳低灌流モデルラットの視索、内包、脳梁において 白質病変の抑制効果が認められた16)。
3)血栓形成阻止作用 脳血栓モデルスナネズミにおいて、血栓形成を抑制し17)、脳血 栓モデルラットにおいて、脳血管閉塞による脳波の平坦化を抑 制した18)。
4)神経保護作用 ラットの海馬神経においてグルタミン酸塩により生じた神経損 傷を抑制した19)。 また、一過性脳虚血モデルラットにおいて虚血による神経密度 の低下を回復した20)。
「血管内皮保護作用」=「血管の壁をまもる作用」というのはあまり見かけない効果です。
強い動脈硬化を良くしよう、という場合に有効かもしれません。
血管の壁に良い効果がある薬剤は、このイブジラストとEPAくらいです。
副作用で見かけるのは食思不振です。
このため薬の副作用が出やすい高齢者に処方する場合には注意が必要です。
他の薬と同じく増量すると効果も高くなりますが副作用のリスクも高まります。
リマプロスト・ベラプロスト(弱い)
リマプロストは「閉塞性血栓血管炎」「腰部脊柱管狭窄症」に、
ベラプロストは「慢性動脈閉塞症」「原発性肺高血圧症」に、
保険適用があります。
手足の冷えなどの場合に内服すると効果がある事があります。
脳梗塞や心筋梗塞に対して保険適用はありません。
以上、動脈硬化の「超まとめ」薬剤編、でした。